第64回天皇杯全日本選手権大会は、日本リーグ2連覇の読売クラブが初優勝、リーグとカップの2冠を達成した。
1965年に日本リーグが発足してから、2冠を達成したチームは七つあり、通算9度目だが、読売クラブの場合は、クラブ組織でプロをめざすための足がかりを固めたという点で、日本のサッカーの夜明けを意味する2冠だったかもしれない。決勝戦のスーパーゴールをあげた川勝−戸塚が、ともに個性派集団のクラブ組織の中で才能を伸ばしたプレーヤーだったのは、それを象徴するかのようだった。
●その1 哲也のスーパーゴールで、新春が来た!!
「すごい。これはことしのゴール・オブ・ジ・イヤーだぞ」
ぼくは記者席で、こう叫んだ。
1985年元日、国立競技場の天皇杯決勝戦。後半なかばの69分に読売クラブ戸塚哲也の先制ゴールが決まった瞬間だ。
この年は、まだ始まったばかり、残り364日もあるけど、1年あとに振り返れば、きっと、元日のこのゴールが、1年間でもっとも、すばらしいゴールだったと思うに違いない。瞬間にそう思ったほど、それはすばらしいゴールだった。
試合のあとで、読売クラブのグーテンドルフ監督は「あれは、本当にスーパーゴールだった」と語った。
加藤久選手も「哲也のシュートはすばらしかった。ヨーロッパでも、めったに見られないようなシュートだった」と言っていた。
古河電工のきびしく、ゆるみのない守りが試合の主導権を握って、0−0のまま終盤にはいろうとしていたときである。
古河の守りにも、さすがに疲れがみえてミスが出たと評した人がいて、ぼくもそうかな、と思ったけれど、あとでテレビのビデオを見てみたら、そうではない。あの場面に関しては、古河の守りに、ミスらしいものはない。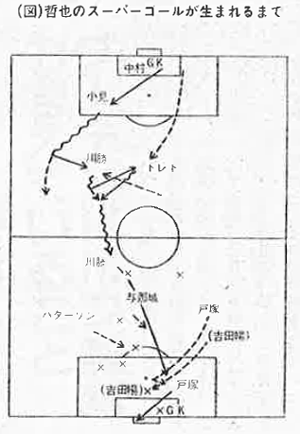
この攻めは、古河のミスからではなく、読売クラブのゴールキックから始まっている(図)。
小見がドリブルで持って上がりかけたところに川勝が走り寄ってボールを受けとる。
川勝は、後方から寄ってきたトレドと、いったんパスを交換してからドリブルでハーフウェーラインを越える。
中盤でのきびしいチェックを避けての、ゆっくりした攻めであり、古河の守備ラインのプレーヤーは、それぞれのマークをつかみながら、ゴール前に戻っていた。
川勝は、ハーフウェーラインを越えたところで、相手のチェックがくる前に、いきなり長いパスをゴール前に送った。そのパスは、左サイドから走り込んできた戸塚に、ぴたりと合った。
走り込んだ戸塚には、マークしていた古河の吉田暢が、しっかりついて走っていた。ペナルティーエリア内にはいってきたとき、戸塚はハーフウェーライン側にいて、マークの吉田暢はちゃんとゴール側にいた。
戸塚は、ゴールと吉田暢を背にして空中を飛んで来たボールを胸で受ける形をとった。
ボールは、戸塚の胸にさわるか、さわらない感じできた。戸塚はそのまま、ボールを外側に流し、自分も外側に身をひるがえし、グラウンドにバウンドしたボールを、左足のボレーでとらえて、矢のようにゴールの逆サイドに突き刺した。マークしていた吉田暢は、この戸塚の反転で一瞬、振り放されてしまった。
ボールのコースとスピードと回転を読んだ戸塚の頭脳は、コンピューターよりも的確だった。内側に走り込みながら外側に反転した駆け引きにはヘビのような感じの冷たさがあった。そして反転のすばやさは、まったくツバメ返しだった。
それまで、実に見事に守っていた古河が、この一発で崩れた。読売クラブの2冠を決めたドラマチックな一発だった。
それまでの両チームの守り合い、とくに古河の守りを土台とした攻守は、サッカーを見慣れた人には、充分に見応えのあるものだった。
しかし、お正月のスタンドを埋めた観衆には守りの試合は物足りなかっただろう。それを哲也のスーパーゴールが救った。
●その2 まるでヒゲの川勝のための天皇杯だった
哲也のスーパーゴールが生まれた直接の原因は、もちろん戸塚の個人の能力である。だが、その前に川勝良一のロングパスのすばらしさが働いていたことを書き落とすわけには、いかない。
このパスの良さには、たくさんの要素がある。
第一にタイミングの良さである。ゆっくりした中盤の攻め上がりで、相手の気持をこちらのサイドに引き寄せておいての逆サイドからの速攻への切り換え。これが利いている。
第二に攻め上がった戸塚とのコンビネーションの良さがある。ポジションは遠く離れていたが、2人は同じ気持で、同じ狙いを頭に描いた。戸塚が走り込むことを川勝は予測しており、川勝がけるであろうボールの種類を戸塚が予想していた。そうでなければ、あんなにぴったりとパスは合わない。
第三に、ハーフウェーラインを越えたところで、逆サイドの戸塚の動きを目に入れた川勝の視野の広さ。これはドリブルするとき、ボールを足もとでしっかりコントロールしながら上体を立てている姿勢の良さにも関係がある。
第四に40メートルほどの距離を低い弾道で飛ばしたキックの正確さ。これは、素質もさることながら、修練の賜物でもあるだろう。 第五に、古河に主導権を握られている試合でチャンスを見のがさずに、持っている力どおりのパスをけることのできた精神的なタフネス。この点では、京都商−法大−東芝とチームを移ってきた川勝が、読売クラブに移ってから、いや、もっと正確にいえば、この天皇杯が始まってから、目に見えて成長したように思う。
なぜ、そんなことを書くかといえば、この川勝のパスを見て、かつて日本代表チームに森孝慈監督が就任したころ、川勝について聞いた話を、思い出すからである。
そのころ川勝は、日本代表のメンバーにはいっていて、森監督は、中盤の組み立て役として川勝が成長することを期待していた。
「センスはいいし、まわりは見えるし、キックは正確なんですよね。ただ、どういうわけか、試合中に大事な場面で、狙いのいい長いパスをちびって、相手にインターセプトされてしまうんです」
森監督が、こういう意味の話をしてくれたことを覚えている。
川勝選手は、当時から鼻の下にひげを貯えていて、ちょっと変わっているな、という印象だった。個性が強いということで、ふつうのサラリーマン選手の型には、はまらないところもあったらしい。
個性派集団の読売クラブに移ってきたとき「心機一転を形で示せ」といわれて、ひげをそり落としたこともあったが、いつの間にか、また生やしている。
川勝は、読売クラブに来てからも、その才能を充分には伸ばせないでいた。
同じ中盤にジョージ与那城がいて、ラモスを使って独特の攻めを組み立てていたから、川勝の攻めの才能には、出番がない感じだった。
ところが、この天皇杯では、ラモスが出場停止で使えないために、川勝の攻めの才能に出番が来た。
グーテンドルフ監督は、攻めの最前線に戸塚とパターソンを並べ、そのすぐ後ろに与那城を置く布陣をとった。 与那城の仕事は、得意のドリブルで仕掛け、あるいはワンツーで中央突破を狙って、相手を脅かすことだった。
川勝は中盤の後方にいて、そこから長いパスを駆使して攻めを動かすことになった。自分の得意なプレーを生かせる仕事を与えられて、川勝は試合のたびに、自信をふくらませていったようだ。
松山で行われた1回戦で大阪体大に先取点されて意外な苦戦をしたとき、同点のPKをけったのは川勝だったし、62分の決勝点は、川勝のけったフリーキックが、パターソンの頭に合ったものだった。
2回戦の帝人との試合では、5得点のうち2点をアシストした。 西が丘の準々決勝、ヤンマーとの試合では、68分に理想的なコーナーキックを、加藤久のヘディングの飛び込みに合わせた。
神戸の準決勝、フジタとの試合では、68分の逆転決勝ゴールに結びつくフリーキックをけった。
そして元日の決勝戦のスーパーパス。才能を伸ばすには、仕事を与え、自信をふくらませる機会を与えなければ、と思った。ともあれ、この天皇杯は、ヒゲの川勝のための大会みたいだったと思う。
|