第63回天皇杯全日本選手権大会は、日本リーグ1部2位の日産自動車が、元日、国立競技場の決勝でヤンマーディーゼルを破リ、創部12シーズンで初の日本一になった。「見る人が楽しめるような攻撃のサッカーで勝たなければ将来はない」と言い続けた加茂周監督。その日産の栄冠は、プロをめざす読売クラブが、日本リーグで優勝したのに続いて、日本のサッカーの新しい時代を予告するものだろう。
果たして最後の釜本か?
1984年1月1日。午後3時8分。試合終了の笛がなると、釜本邦茂は、枯芝の国立競技場のフィールド中央に、腰に手を当ててしばらく立ちつくし、やがて選手たちひとりひとりに握手を求めて回った。
「やはり、釜本は選手引退かなあ」
と、思わせるシーンだった。
「この天皇杯で釜本はやめる」
そんな噂は、大会の前からあった。ヤンマーが勝ち進むと、決勝戦当日の朝の紙面に、「釜本、きょう最後の大舞台」と派手な見出しをつけたスポーツ新聞もあった。
釜本自身は、決勝戦の試合のあとも「まだ決めてない」と、そっけなかったが、あのタイムアップの瞬間のぶぜんとした姿が、この偉大なストライカーの最後のユニホームだとしたら、その映像を、しっかりと脳裏に焼きつけておかなくてはならない。
釜本が選手たちに握手を求めて回っているとき、日産のマリーニョは、選手たちをうながして、正面スタンドの方に向かおうとしていた。
天皇杯では、決勝戦のあとの表彰式を、正面スタンド中央のロイヤルボックスで行う。ワールドカップやイングランドのFAカップの表彰式と同じやり方で、選手たちがスタンドへ上がって行き、高いところでカップを受けとる。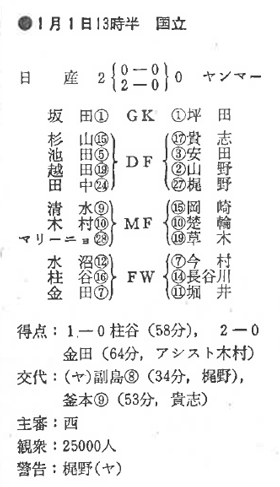
このやり方は、日本ではなじみが薄いので毎年、初優勝したチームの選手たちは、とまどうのだが、マリーニョは、フジタにいたときに2度、天皇杯で優勝しており、これが3度目だ。表彰式のやり方に、とまどうことはなかった。
水沼、柱谷、田中、越田……。日産の若い選手たちは、みな、とてもうれしそうだった。
しかし、喜び爆発、といった感じではなく、ちょっとばかり控え目にしていた。カップを手離さずに、ビクトリーランでも、終始先頭に立っていたのは、栗色の髪のマリーニョだった。
釜本、マリーニョ、そして日産の若い選手たち。
これは、日本のサッカーに転換期が来たことを象徴するようなシーンだ――と、ぼくには思えた。
日本リーグでは読売クラブ、天皇杯では日産と、ともに歴史の浅いチームが優勝して、日本のサッカーは、音を立てて回り始めた。
タレントを活用した日産
表彰式では、ちょっと遠慮がちだったが、試合では、日産の若い選手は、のびのびとプレーした。とくに、法大からはいってまだ1年目の水沼貴史君が目立った。
決勝戦の立ち上がり5分、水沼が長いドリブルで抜いて、ゴールを狙った場面があった。20分にも水沼の独走ドリブルがあった。これはヤンマーの梶野のトリッピングに倒されたが、梶野はこれで警告を受けた。
「昔だったら、新人があんなにドリブルしたら叱られたんじゃないか」
と記者席で冗談が出た。
雲ひとつない快晴。おだやかな日よりに恵まれて、スタンドの観衆は2万5千。こちこちになるはずの決勝の舞台で、いきなり新人が、自分の得意なプレーを大胆に出せるところにことしの日産の良さがあった。
もっとも、浦和南で高校サッカーのスターだった水沼君にとっては、天皇杯の決勝ぐらいは、たいした重圧ではなかったかもしれない。なにしろ、天皇杯よりも高校選手権の方にずっと人気も重みもあるのが、日本のサッカーの現実なのだから。
水沼君は、準決勝のフジタとの試合では、1得点、1アシストで勝利の原動力となった。この天皇杯、活躍したのは水沼君だけではないけれど、新人の才能を、これだけ、のびのびと活用できたところに、日産の良さがある。
いま、高校ではすばらしい選手が育ってきている。高校がすばらしいチームを作っている。その勢いを、大学や日本リーグのチームが止めてしまわないようにして欲しいものだと水沼君の活躍ぶりを見て思った。
日産サッカーの成功の大きな原因は、若い選手の才能を生かし、活用できたところにある。
昭和55年に金田喜棯(中大)、56年に木村和司(明大)を入れ、58年には水沼のほか、柱谷幸一(国士大)、越田剛史(筑波大)と、日本代表クラスをつぎつぎに加えた。
「日産は金の力で選手をかき集めている」というかげ口も聞かれた。
しかし、タレントを集めるだけでは、いいチームはできない。才能のある若い選手を集めているチームはほかにもある。ところが、多くのチームは、せっかく集めたいい素材を生かせないでいる。生かせないどころか、選手の方がいやになって、逃げ出そうとするケースが一、二にとどまらない。
「近ごろの若い選手は……」という声をよくきくが、若い選手を生かせない側にも、大きな欠陥があるのではないか。
その点で、日産の加茂周監督はよくやったと思う。いい選手を集めたのは事実だが、それを活用できたのも事実である。この選手たちが、今後もぐんぐん伸びて欲しいと思う。
大会通算22得点は新記録
優勝後の記者会見で、加茂監督は
「これまでのやり方ではいかんと思い始めたのは、5年前です」
と話した。
昭和54年に日本リーグ1部に昇格したが最下位。そのころはまだ、他の1部のチームに比べれば、いい選手もいなかった。だから強い相手の攻撃に耐えて、守りに守らなければならなかったのだが、
「いつまでも、こんなことをしていては、永久にはい上がれない」
と思った。
ドリブルがうまく、攻撃型のプレーヤーである金田がはいってきたのを機会に、「負けてもいいから攻撃的なサッカーを」と方向転換をはかった。
「そうしたら、案の定、2部落ちでした」
いまだから加茂監督は苦笑ですませることができるが、会社から大きな援助をもらってチームを運営している身にとって「すぐ戻れる」と信じてはいても、2部へ落ちる危険をおかすのは大変なことである。それをあえてした加茂監督の英断は立派である。
ちょっと横道にそれるが、それにつけても、1、2部の間の入れ替え戦を廃止しておいたのは良かった。
おそらく、加茂監督は、2部に落ちても、2部で優勝できることには自信があっただろう。2部で優勝すれば、1部の最下位と自動入れ替えである。いま、1部9位と2部2位は入れ替え戦をやっているが、これも将来、1部のチーム数を増やすような機会に、廃止した方がいいと思う。
話を本筋に戻そう。
2部に落ちたけれども、加茂監督は、攻撃的サッカーをめざす方針を変えなかった。
「幸いに、すぐ1部に戻れて」いよいよ日産の「攻撃のサッカー」は本格的になる。
木村がはいって、金田とのコンビができた。決勝戦の2点目、54分のゴールは、ハーフライン付近から木村の出した浮き球のタテパスが、前線に走り出る金田にぴたりと合ったものだった。金田はバック2人を振り切り、さらにゴールキーパーもかわしてシュートした。
この木村−金田で攻撃のサッカーの軸ができた。
58年にはいってきた新人たちは、この軸にからんで伸びた。
決勝戦の1点目は58分。左からの金田のセンタリングが右に大きく切れたのを、木村が追って右ライン近くから折り返す。ゴールキーパーがいったん止めたが、こぼれたのを柱谷が決めた。
決勝戦だけでなく、どの試合でも、木村−金田に若手がからむ攻めが生きていた。
決勝大会5試合で22得点。これは天皇杯が現在の方式になってからの新記録である。
|