銀の天皇杯が黄色いユニホームの手で高く頭上にかかげられたとき、金髪のマリーニョは、喜びで顔をくしゃくしゃにしながら、夢中で自分のチームの栄冠に自分で拍手を送っていた。1978年元旦、第57回天皇杯全日本選手権大会の決勝戦――マリーニョ、カルバリオらブラジルからの移入選手3人を主力にするフジタ工業は、釜本のヤンマーを4−1で破って初の「日本一」のタイトルを獲得した。
ブラジル選手の足わざを武器にしながら、ヨーロッパ風のチームプレーの影響もちらりとみせ、しかも日本的ながんばりを支柱にしている不思議なチーム。このフジタの初優勝は、新しいスタイルのサッカーを日本で生み出したものだろうか? そして、これは新しい時代のはじまりなのだろうか?
雨中の攻め合いの決勝戦
雨だったけれども、珍しく暖かいお正月だった。フジタ−ヤンマーの決勝戦に、国立競技場のスタンドを埋めた観衆は、協会の発表で約3万。お天気が悪かったわりには、まずまずの人気だろう。競技場にきてくれた人たちは、本当にサッカーを愛しているファンの中のエリートだったにちがいない。
お天気が悪いといっても、試合の内容に大きく響くほど芝生は荒れていなかった。前半のなかばに、急に強く降りはじめ、グラウンドがすべるようになって、27分ごろにフジタのカルバリオが、ベンチに近い、タッチラインのところへ出てシューズをとりかえたが、降りがひどかったのはこのときだけで、後半には、ほぼ上がっていた。
カルバリオが、試合の途中でシューズを取りかえたのは、ちょっと興味深かった。スタッドの低いものと高いものと2足のシューズを用意しておいて、コンディションに応じて使いわけるのだろうが、日本の選手がゲーム途中にはきかえる場面は、めったに見たことがない。外国の試合では1974年のワールドカップのときに、オランダのヨハン・クライフが試合中にはきかえ、マークしている相手の選手が、そのそばにじっと立ってついていたので、思わず笑ったことがある。翌日のドイツの新聞にクライフがトイレに行ったらマークしている選手もトイレに行っただろうかと冗談がのっていた。
それはともかく――。
カルバリオが試合中にシューズをはきかえたのは、やっぱりブラジル的感覚なんじゃないか、という気がする。日本チームにはいって、ものおじせずにブラジル風のやり方をし、それが少しも不自然でなく、チームの中にとけこんでいる。そこにフジタの不思議なチームカラーがあるように思った。
結果としては、決勝戦は4−1でフジタの快勝だった。だが、試合の内容は、ヤンマーにも数多くのチャンスがあり、活発な攻め合いの、楽しめるものだった。
立ち上がりの1分と3分に、吉村のフリーキックに釜本が飛び込んでヤンマーに惜しい場面があった。これが先制パンチになっていれば、あるいは勝敗が逆になっていたかもしれない。
しかし、形勢はしだいにフジタ有利になっていった。それはフジタのほうが、より正確に、より確実にボールをつなぐことができたからである。ヤンマーは吉村−釜本が頼りだったが、フジタはどの選手からどの選手にパスがつながっても、一つ一つが確実なねらいをもっていた。
前半33分にフジタが先取点をあげた。左コーナーキックを比嘉がけり、渡辺三男がゴールキーパーの前に飛び込んで、高いヘディングで決めた。
だが、この時点では、まだフジタの優位は決定的だったわけではない。後半のはじめの10分間にも、ヤンマーはたて続けにチャンスをつくった。8分、正面のペナルティー・エリアすぐ外のフリーキックを釜本が右足でカーブをかけて守りの上を抜き、右ポストとバーの角にあてたのは特に惜しい場面だった。
12分、吉村の中盤左からのフリーキックをゴール右で釜本がヘディングでつなぎ、上西が決めでヤンマーは同点に追いついた。
しかし、そのあと1分もたたないうちにフジタは再びリードを奪う。これが決定的だった。釜本からのパスをインターセプトし、古前田、カルバリオと縦につないで逆襲、比嘉が突っ込んで、ブラジル・コンビであっという閧にゴールになった。
22分に古前田が右からドリブルで攻め込み、水口のまたの間を通しで抜き、ゴール前へ低く通したのをヤンマーの坂野が足に当ててけり込む自殺点。40分に脇が左から攻め込み、比嘉にかわって後半34分から出ていた新人の植木が追加点、点差は実際の形勢以上に開いた。
どこからでも燃えはじめる
フジタの栄冠は、日本のサッカーにとってどんな意味があるのだろうか。石井監督は、決勝戦のあとのインタビューで、こんなことをいっていた。
「ヤンマーのサッカーとフジタのサッカーの違い。それがあるとすればうちはどこからでも攻められるというところでしょうか」
たしかに、そこにはフジタのサッカーの特徴がある。
決勝戦の前半15分、得点にはならなかったけれども、こんな場面があった。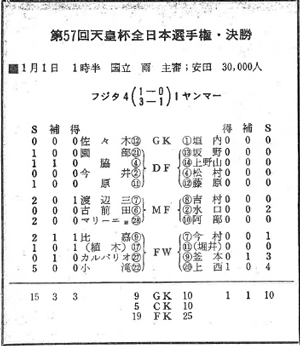
中盤左サイドで渡辺から比嘉に短いパスが出る。比嘉から折り返しパスを受けてラインぞいに突進したのは、左フルバックの原だった。原のセンタリングを小滝がフリーでヘディングし、ボールは惜しくもゴールキーパーの正面だった。
後半40分のフジタの4点目をアシストしたのはスイーパー役の脇だった。脇はスイーパー役というもののかなりの時間をバックラインより前でプレーしていた。また左フルバックの原は、左のウイング・フォワードといっていいくらい、積極的に攻めあがっていた。それでいてフジタの守りには乱れがなかった。
比嘉、マリーニョ、カルバリオのブラジル・トリオの足わざと勝負強さは、もちろんフジタの主要な武器だった。しかし、フジタの攻め手は、それだけではなかった。今回の天皇杯では、マリーニョとカルバリオが本調子でなく、それが準決勝までの苦戦の原因になっていたが、チャンスはバックラインの脇からも原からも園部からも、また中盤の渡辺、古前田からも生まれた。
ボールがつながって渡った先のいたるところから、つぎつぎに火の手があがり、それがたちまち燃え広がるという感じだった。
これに対し、ヤンマーは吉村−釜本のラインが強力な、しかし、ただ一つの決め手だった。決勝戦の前にフジタの石井監督は「ヤンマーは徹底的に釜本にボールを合わせてくるだろう」と選手たちに注意したというが、そのとおりにヤンマーは釜本を先頭に立て勝負を挑んできた。
吉村−釜本のラインを武器にするヤンマーが、日本のサッカーに一つの時代をつくったことは確かである。ヤンマーは過去10年間に7回も天皇杯の決勝に進出している。吉村に集め、釜本につなぐサッカーがつくった、これは一つの偉大な記録である。
このヤンマーのサッカーを、特に強力な火つけ役はいないが、どこからでも燃えあがるフジタのサッカーが破った。ヤンマー時代が終わってここからフジタの時代が始まるのだろうか。
結論を出してしまうのは、まだ早すぎるかもしれないが、転換の可能性を示した天皇杯だったとはいえるだろう。
「ヤンマーは徹底的に釜本に合わせてくるだろうから、こちらは徹底的にサイドからえぐっていこう」と石井監督は指示したという。サイドからえぐったのが、ウイングのスペシャリストではなくて、中盤のプレーヤーだったり、スイーパーだったりしたところに、フジタの新しさがあった。
もう一つつけ加えれば、積極的に攻め上がりながら守りに乱れを見せなかったフジタのローテーションの良さは、1974年ワールドカップのオランダに似ているところがあった。「ぼくはディフェンスしろという言葉は使わないんです。ボールをもっている相手に攻撃的なプレッシャーかけろ、というんです」という石井監督の表現は、オランダの集中守備を「ボール狩り」と称していたミケルス監督と共通しているのではないか。
|