今回の天皇杯の表彰式は、ヨーロッパ・スタイルだった。優勝した日立の選手たちは、小畑主将を先頭に、メーンスタンドの観衆をかき分けるようにして階段を上がり、銀色に輝く天皇杯を、ロイヤルボックスで受けた。これまでのようにフィールド上に整列してうやうやしくおしいただく日本式の表彰よりも、ずっとスマートで、さわやかだ。これも一つの改革であり、進歩である。
しかし――。
かんじんのゲームの内容は、どうだったか。日本のサッカーの将来に希望を見出せるような改革や進歩があっただろうか。
●高橋用兵によみがえった日立
――松永を生かした質のいい労働量
元日の決勝戦は、すばらしいお天気に恵まれた。
明るい陽射しが、国立競技場のバックスタンドを埋めたお客さんを包んでいた。コーナーフラッグは静かにボールに巻きついている。風のない、暖かなお正月だった。
日立製作所−フジタエ業。
天皇杯のファイナルは、意外な顔合わせである。
おだやかなお天気とは逆に、フィールドの上では、激しい闘争が展開されるだろうと予想されていた。
日立は、2年連続の2冠王をねらったヤンマーを、激しい当たりで粉砕しての決勝進出である。
一方のフジタも、リーグ7位の不成績をはね返そうと、動きの激しいサッカーで番狂わせを起こして進出してきた。
激しさと激しさの対決。
それが日本一を決めるだろうと見られていた。
しかし、実際に勝負を決めたのは、激しい当たりでも、激しい動きでもなかったように思う。日立が快勝したのは。当たりと動きの激しさの“量”が多かったためでなく、“質”がフジタよりも良かったためである。
前半は0−0。
記録用紙を見ると前半のシュート数は8−4で日立のほうが多いけれども、フジタは中盤の古前田がチャンスを作り、形勢は互角だった。特に前半終了少し前の42分に、古前田が大胆なドリブルでゴール正面を目ざし、日立のスイーパー川上を抜き、GK瀬田もつり出しながら、勢い余ってラインを割ったのは、フジタにとって惜しい逸機だった。
だが、後半の形勢はがらりと変わった。記録用紙の上のシュート数は7−4で今度はフジタのほうが多い。しかし、試合の主導権を握っていたのは日立のほうである。
勝負を決めた日立の2点は、ともに“ゴール前のハイエナ”松永章がとった。その松永の動きについて、日立の高橋英辰監督は試合のあとで報道陣に次のように説明している。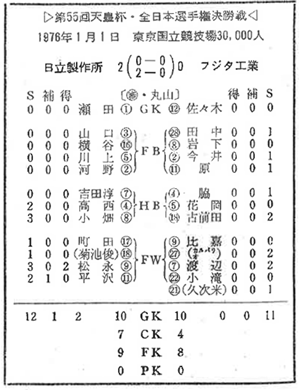
「松永がまん中にいると相手の激しいマークにつぶされるからね。右か左に開いて待つように指示したんですよ」
一方、松永自身は、シャワーを浴びたあと、ロッカー・ルームでこういっていた。
「監督には、ゴール前で、まっ正面から勝負しろ、逃げるな、といわれました」
この二つの証言は、一見、矛盾しているように見える。しかし、2人の言葉がともに事実であることは、後半の2点の得点経過を見ればわかるはずである。
63分の1点目。
中盤の右ライン寄りでボールをとった菊池俊がドリブルで内側に向かう。そして内側から交差するように走り出た平沢にパス。平沢はドリブルでフジタの守備をかわしてゴール前逆サイドヘクロスパスをあげ、左サイドから走り込んだ松永が、身体を思い切って前へ抜け出して、みごとなダイビングのヘディング・シュートを決めた。
2点目はその10分後の73分。
逆襲のボールを右サイドで菊池俊が受け、後方から内側を走り上がってきた高西にパス。高西がすぐに左サイドへ振り、右から左へ斜めにフィールドを横断したパスに、松永が左サイドから走り込んで迫いつき、スピードを落とさないドリブルでバックをかわしてゴールへ独走。飛び出してくるゴールキーパーの佐々木も外側へかわして、左ポスト前の角度のないところから落ち着いて転がし込んだ。
2点とも松永は、ボールのある場所とは逆のサイドから走り出て、ゴール前では思い切ったプレーで相手を“打ち負かして”いる。「左右へ開いて待て」という指示と「ま正面から勝負しろ」という指示が、両方とも日立の2点の中に、生かされていることがわかる。
3年前「走る日立」をモットーに、リーグとカップの2冠をとったとき、日立のサッカーの特徴は、労働量の多いことだった。
今回も、平沢、小畑を中心とする中盤の労働量は日立の武器だった。特に平沢の動きの良さは、今回の天皇杯獲得の最大の原動力だったということができる。
だが、その労働を得点に結びつけることができたのは、高橋監督の用兵のうまさによるところが大きい。
いかに労働の“量”が多いようにみえても、それがチームプレーに生かされなければムダ骨折りである。中盤の労働の“質”をあげることによって、ゴール前での松永の能力を生かそうというねらいが、少なくとも決勝戦に関しては鮮やかに成功していた。
|