天皇杯を盛り上げるために、読売クラブ優勝の意味を考えサッカー協会の努力を望む!
元日の天皇杯決勝は読売クラブがマツダを破って2年連続3度目の優勝を飾った。準々決勝が4試合とも引き分けでPK戦になるという実力伯仲の戦国天皇杯。読売クラブは準決勝でも古河電工と引き分け、PK戦で生き残るという苦しい戦いの末の優勝だった。
決勝戦は南米スタイルの読売クラブと欧州人監督が率いるマツダの異色対決で内容のある好試合。読売クラブはすべて選手が持ち味を存分に出してタイトルを守った。
与那城カラーの成功
準々決勝のラモスのスーパーゴールが決勝戦で全員の個性をフル回転させた
天皇杯で3度、日本リーグで3度の読売クラブの優勝の中で、今回の天皇杯がもっとも読売クラブの良さが出た優勝だったのではないだろうか――快晴と異例の暖かさに恵まれた国立競技場の貴賓席で松木主将が天皇杯を高々と掲げるのを見ながらそう思った。
準々決勝と準決勝が引き分けでPK戦、苦しい戦いのすえの優勝だから、すっきりした勝ちっぷりだったとはいえないのだが、ジョージ与那城が16年前にブラジルから来て以来、ジョージのテクニックと個性を中心に作られてきた読売クラブのサッカーの良さが、この天皇杯ほど端的に表現された大会はなかったのではないか。与那城監督は就任してまだ2年目だから、こういうことを言うのは早過ぎるのだけれど、今回の天皇杯は、与那城のサッカーの集大成だったような気がする。その一つの表れはラモスの活躍である。
ジョージ与那城の少年時代の友達だったラモスは、日本に来て12年目になる。ラモスが日本に来ることができたのはジョージのお陰だったし、読売クラブで力を伸ばすことができたのも、選手のころのジョージとコンビを組んだお陰である。
ジョージが監督になって2年目の今回、ラモスは、その恩義に見事に報いた。怪我や出場停止でフルに活躍できないことも多かったラモスだが、今回は終始、チームの中核として活躍した。その象徴が準々決勝での鮮やかな同点ゴールである。
12月27日に東京の西が丘で行われた試合で、前半30分に本田がペナルティーキックによる先制点をあげた。
このペナルティーは読売クラブにとっては、はなはだ酷なものだった。本田のシュートが守りにはね返されてペナルティーエリアの外にこぼれ出たのを、本田の神戸がすかさず、もう一度シュートする。それが密集の守りの中にいたラモスの身体に当たった。
ラモスは手を広げたり、上げたりして止めたわけではない。相手が力いっぱいけったボールが身体にぶつかったという感じだった。
こういうケースは主審が「インテンショナルでない」として反則にしなくてもいい。普通は反則を取らないケースだと思う。現に、このあと本田の方に似たケースがあったのに見逃している。この試合の主審はふだんに似ず出来が悪かった。ともあれ、これは読売クラブにとっては不運なペナルティーキックだった。
だが、その直後のキックオフからの攻めでラモスが見事にこの不運をはね返した。
センターサークルから右へ、戸塚-武田と渡ってきたボールを、ラモスは空中に足を浮かせてさばき、身体を寄せてきた相手の背後に出してすり抜け、落ちてくるボールをそのままボレーのミドルシュートでたたきこんだ。
このシュートは、ラモスの生涯の中でも思い出の会心のシュートになるのではないか。ペレが1958年のワールドカップでデビューしたときに見せたという伝説のプレーを思い出させた、といったら大げさだろうか。この試合のテレビ中継がなかったのが残念である。 また、このすばらしいシュートを翌日の新聞があまり特筆しては取り上げなかったのも残念である。
結局、この試合は延長のすえ引き分け、PK戦となり、新聞はもっぱらPK戦の話を書いていた。しかしPK戦は抽選の代わりであって、そんなに大きな意味はない。ラモスの同点シュートがなければ、この試合はきわめて後味の悪いものになっていたはずである。
3日後の準決勝、5日後の決勝戦を、読売クラブの選手が、与那城監督のもとに全員が個性をフル回転させて戦うための、これは伏線になったと思う。
マツダの守りの不運
決勝戦の1点目はオフサイド? 前に出て守るマツダには辛い判定だった!
30日の準決勝。読売クラブは神戸で古河電工と対戦した。1年前の天皇杯は、古河がアジアクラブカップ出場のため棄権し、その留守に読売クラブが優勝したので、これは前回は見られなかったカードというわけで興味を呼んだが、0-0で引き分け。PK戦で読売クラブが決勝に出た。
東京の国立競技場でのもう一つの準決勝はマツダが延長のすえ住友金属に勝った。マツダが相手の自殺点で先行し、住金はペナルティーキックを得ながら失敗するなど、同点にしたもののこちらは得点はあったが凡戦だったようだ。
さて元日の決勝戦――。
これは、決勝にふさわしい好試合だった。
読売クラブは松木主将をはじめ全員が、すばらしいプレーをした。
昨年は千疋にポジションを奪われて出番のなかった都並が左のバックのポジションで積極的にプレーした。前に出て勝負して抜かれる場面が何度かあったが、その後を加藤久が見事なタックルでカバーした。全員が良かった読売クラブだが、加藤久の守りの技術と頑張りは準決勝の古河戦での活躍に続いてとくに光っていたように思う。
結果は2-0で読売クラブの快勝だった。攻守の内容と試合の形勢からみて、順当なスコアだが、ただ、読売クラブの先取点にオフサイドの疑いが濃いことは指摘しておかないとマツダに対して不公平だろう。
この得点は前半終了間ぎわの44分。大友のシュートが、前に出て守ったゴールキーパーのディド・ハーフナーに当たってはね返ったのを、トレドがけり込んだものである(図1)。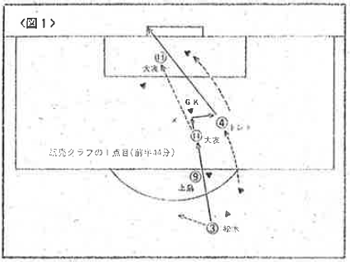
走り込んでシュートした大友は、勢い余ってゴールキーパーの上を飛び越えてゴール前に出た。そのためにトレドがシュートしたときに大友はオフサイドの位置にいた。線審はすぐ旗を上げ、主審は線審のところに駆け寄って協議したがゴールを認めた。
ゴールを認めたのは、オフサイドの位置にいた大友が実質的にトレドのシュートに対するマツダの守りに影響を与えていない、と判断したからだろうと思われる。
実際、これは一瞬のうちに、プレーの流れの勢いで起きた場面で、意図的にオフサイドトラップを掛けた場面ではなかった。
しかし、トレドのシュートと大友の位置は極めて近い。過去にこういうケースは、ほとんどオフサイドを取ったのではなかったか。
マツダは浅い守備ラインを敷いて前に出るオランダ流の守りを採用している。ハンス・オフト監督が、前に強いゴールキーパーのディド・ハーフナーをオランダから連れて来たのは、この戦法を使うためである。こういう戦法は、オフサイドを、どんどん取ってくれないと成り立たない。
前半終了間ぎわという時間帯と相まって、このオフサイド無視は、マツダにとって極めて痛かったといえるだろう。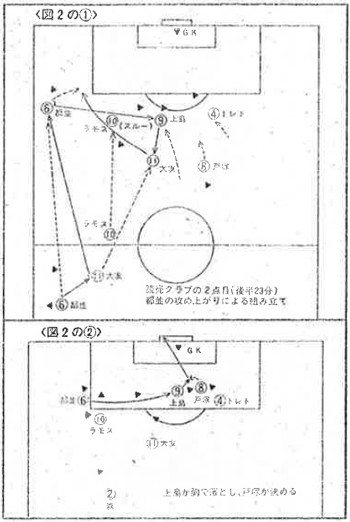
読売クラブの2点目は後半の23分。後方で都並が相手に競り勝ってボールを奪い、その足で攻め上がったところから始まる見事な組み立てによるものだった(図2の①)。
スピードと技術とアイデアを生かした攻めで、全員が個性を存分に発揮した今回の読売クラブの良さを絵に書いたような鮮やかさだったが、ここでも最後のシュートのとき、上島が胸で落としたボールを、走り出て受けた戸塚はオフサイドぎりぎりだった(図2の②)。
浅い守備ラインによる守りは、このような危険と紙一重である。
そういう意味で、得点場面だけを取り上げれば、マツダに不運があったともいえるし、読売クラブがよく、その弱点をついたともいえるだろう。
|